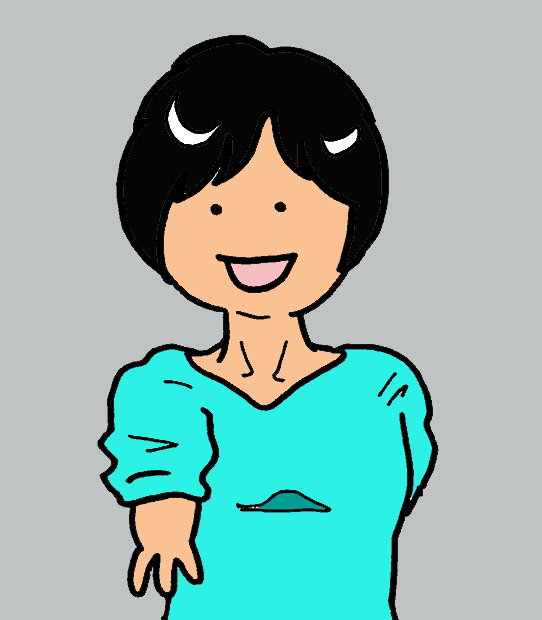〈スポンサーリンク〉
“障害“とは何か? その2
以前に「障害とは何か」というテーマでエッセイを書かせていただきました(→こちら)。
障害は個人の属性ではなく、社会の環境や人間関係の中で決まるということを述べました。
例えば聴覚障害者もコミュニティの全員が手話を使える環境であれば、
聴覚障害は全くハンディキャプになることはありません。

以前僕が訪れたことのある施設では、聴覚障害者が多く、共通言語の一つは手話でした。
僕は食事の時の楽しい会話にも参加できず、
そこでは自分がハンデを持っているような感覚に陥りました。
つまり社会の環境が変わることによって障害が障害でなくなるという新しい手がかりを感じました。
今回はこの話題をもう少し進めたいと思います。
手に障害を持つ女性の話
サリドマイド福祉センター常任理事の増山ゆかりさんが、以前テレビでこんな話をしていました。
彼女はサリドマイドの影響で、上肢は短く、指は3本しかない奇形を持って生まれました。
彼女がまだ小さい時は、手を補うように足でフォークを持ち、不自由なく食事が取れていました。
しかしある時からリハビリで「これからは手を使って食べましょう」と手の機能訓練が始まりました。
今までのように足を使えば問題なく食事ができたけれども、
それでは社会に出でから困るだろうとの理由で、動きの悪い手に装具をつけて訓練を行いました。
リハビリ側としては
「できることなら健常に近いかたちにしてあげたい」
という善意の気持ちだったと考えられますが、
その時増山さんが感じたことは、
「ありのままの自分は受け入れてもらえないのだろうか」
ということだったそうです。
多分リハビリでは一種のパターナリズムというか
「この子は将来手が使えた方が社会に適応しやすいだろう、生きやすくなるだろう」
という親心からそうしていたんだろうと想像しますが、
増山さんは当時を振り返って、別な考えを述べています。
「足を使うことで何も問題なかったのに、あえて手を使うことを禁止したのには、足を使うことを恥ずかしいという気持ちがスタッフの心の底にあったのではないか」
と言うのです。

なかなか興味深い指摘ですね。
足で食事をすることに何の問題もなく、本人はその必要性を感じていなかったのに、
先回りして指導したのは、悪気はなくても手を使うことが当たり前という偏見があったと思われます。
彼女にとってリハビリ訓練は屈辱だったと後になって語っています。
足で食事を摂ることを社会が普通に認めるならば苦しいリハビリをしなくとも済んだ。
世間がより成熟して寛容であったなら、彼女の自尊心が傷つくこともなかったでしょう。
このように社会の理解が進むことで、「障害」が「障害」でなくなる場合も多いと思います。
完全に治らない障害を治すことに力を注ぐことで、
彼らの貴重な時間を奪ってしまうことにもなる。
ある程度生活できるのであれば、障害に固執させることなく、社会に送り出すことも必要でしょう。
予後の見極めが大切
リハビリを含め医療者側は「治療」という視点から離れられません。
もちろん完治が望める場合は、病前の状態に戻すことを目標にすることも大切です。
ですが完治が望めない場合、そこに固執させるのは罪です。
そもそも患者も完治を望んでいない場合もあります。
お互い十分にコミュニケーションをとり、目標共有をしておくことが大切ですね。
ありがとうございました。
〈スポンサーリンク〉