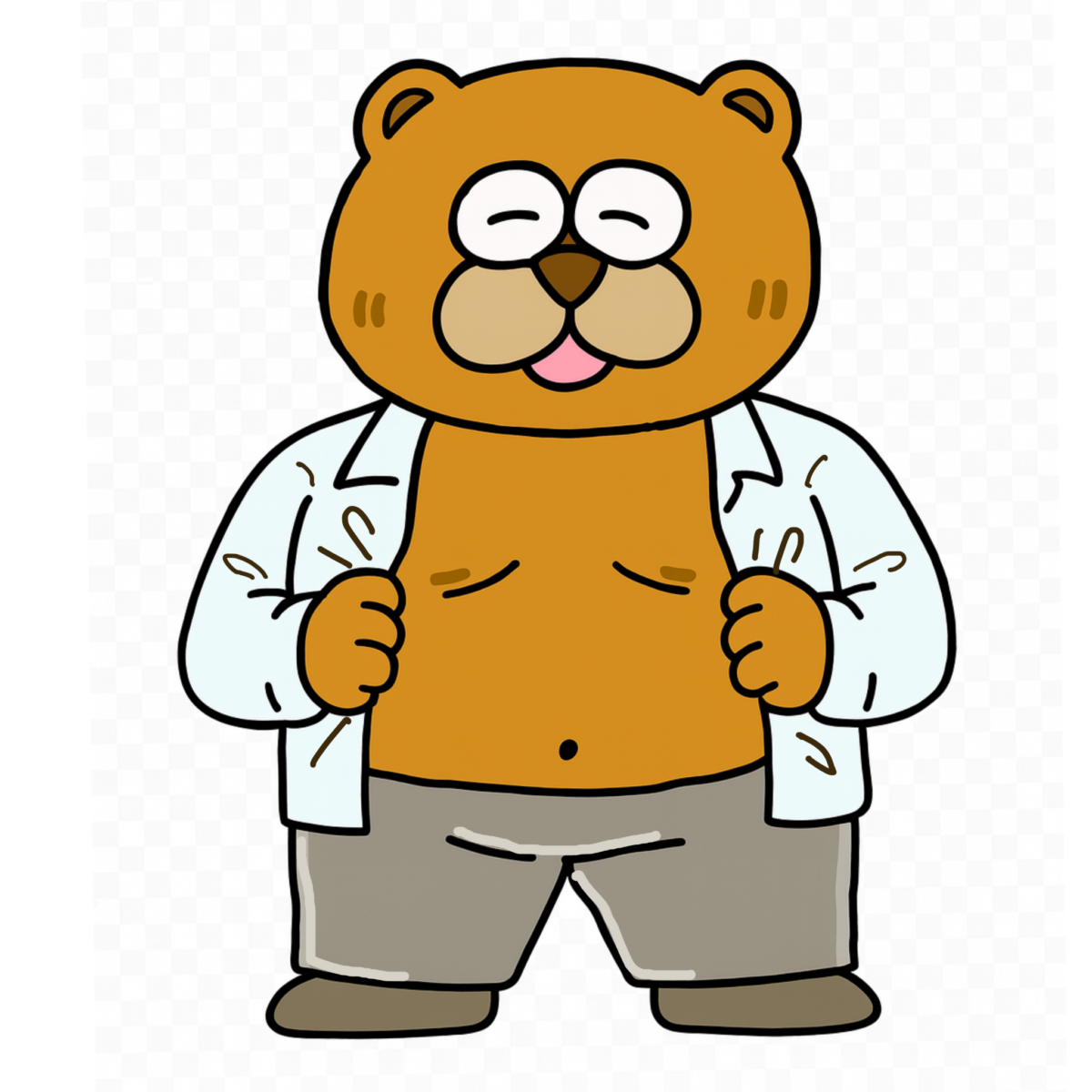〈スポンサーリンク〉
相手の心を開かせる一つの方法、それは自己開示
人と話をしていて、「この人には心を開けるな」と感じる瞬間があります。
それは、相手が少しだけ自分のことを話してくれたときではないでしょうか。
医療やリハビリの現場でも、同じことが言えるように思います。
私もよく患者さんに「今日は調子はいかがですか?」と尋ねるのですが、単にそれだけでは会話が途切れてしまうことが少なくありません。
そんなときに「実は私も最近、腰を痛めてしまって…」と軽く自分のことを話すと、患者さんがふっと笑って「先生でもそんなことがあるんですね」と返してくれる。
その瞬間、空気が少し柔らかくなるのを感じます。
ああ、こういうことなんだな、と。
こちらが少しだけ心を開けば、相手も安心して心を開いてくれる。
ただ、この“少しだけ”というのが難しい。
では、どこまで話すか?
自己開示は相手との距離を縮める強力な方法ですが、深すぎる話は逆に相手に負担を与えてしまうことがあります。
私も何度か「あれは話しすぎたかもしれない」と反省したことがありました。
その加減をどこで見極めるか。
結局のところ、相手にとってそれが「安心」や「共感」につながるかどうかがひとつの目安になる気がします。
患者さんが「自分のことを話しても大丈夫なんだ」と感じてくれたなら、それは良い自己開示だったのでしょう。
一方で、相手が「大変ですね」「それは困りましたね」とこちらを気遣うようになってしまうと、もうそれは“共有”ではなく“負担”になっています。
自己開示は、深さを競うものではありません。
むしろ、相手との距離や空気を感じ取りながら、少しずつ階段を下りていくように話を重ねる。
そのなかで自然に心が通い合う瞬間が生まれるのだと思います。
リハビリの現場でも、人生のどんな場面でも。
「どこまで話すか」は正解のない問いですが、
きっと大切なのは、“相手のために話す”という姿勢なのかもしれません。

まとめ
自己開示は、相手の心を開くカギになり得ます。しかし同時に、その加減を誤ると逆効果になってしまう難しさがあります。
私自身も試行錯誤を重ねながら「どこまで話すべきか」のラインを探っています。
大切なのは、「相手にとって安心や共感につながるかどうか」。
それを基準に自己開示を選んでいくことが、良いコミュニケーションへの近道になるのだと思います。
〈スポンサーリンク〉