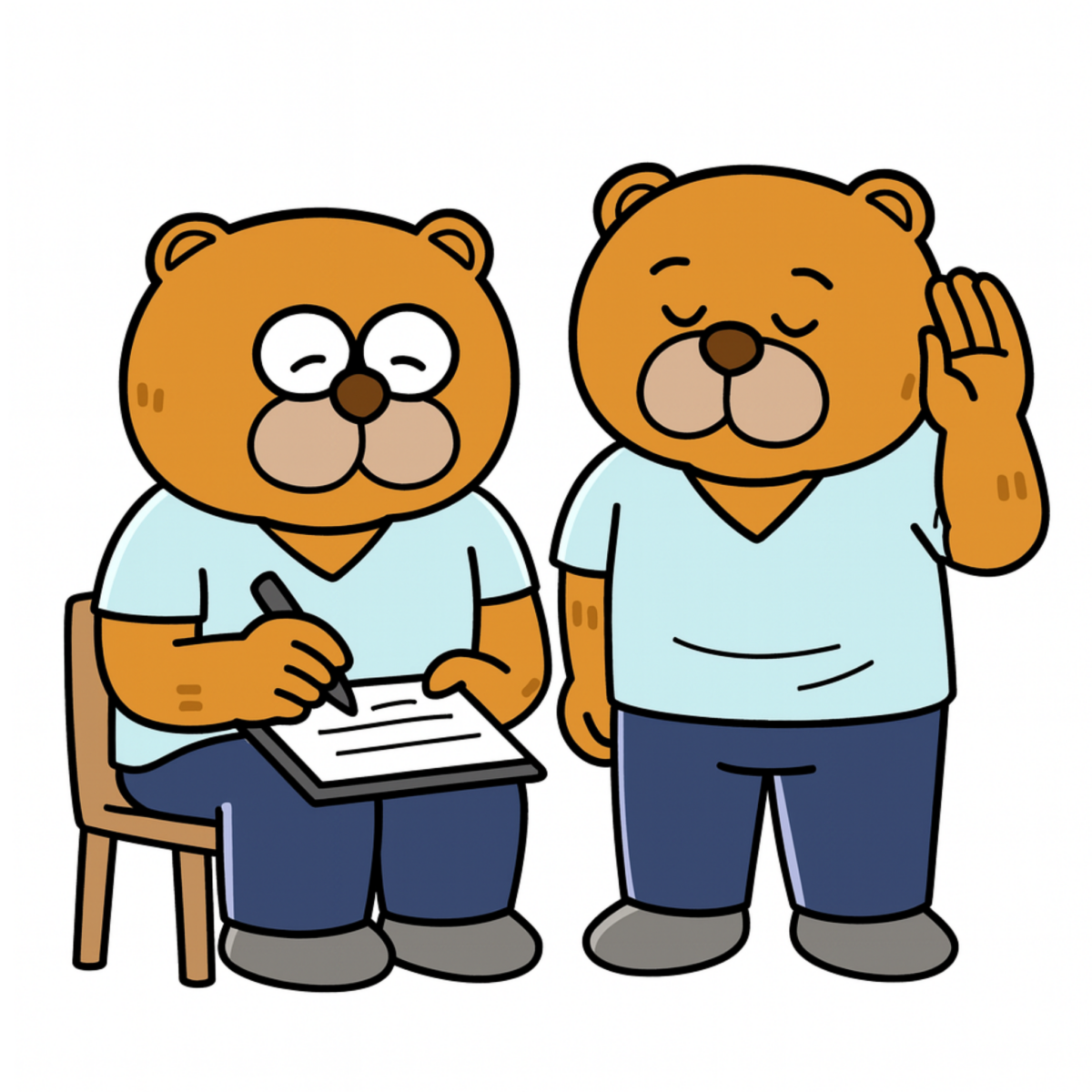〈スポンサーリンク〉
聾者や難聴の方へのリハビリで大切にしたい配慮
僕自身も難聴ですが、リハビリの現場ではときに聴覚に障害を持つ方や、高齢による難聴が進んだ方を担当することがあります。
聴覚からの情報が制限されると、私たちが普段何気なく行っている声かけや説明がそのまま伝わらないことも少なくありません。
そのため、相手に合った方法を工夫することがとても大切になります。

聾者のリハビリで気をつけること
聾者の方と関わる際には、まずどのようなコミュニケーション手段が一番伝わりやすいかを確認することから始めます。
僕は手話ができないため、筆談や文字アプリを活用してやり取りすることが多いのですが、最初に「どの方法がやりやすいですか」と尋ねるだけで安心感が生まれます。
言葉だけではなく、表情やジェスチャーを積極的に取り入れたり、実際の動きを見せるなど視覚的な情報を増やすことも効果的です。
また、相手の表情がよく見えるように正面に立ち、明るい環境で説明することも重要な配慮だと思います。
筆談やアプリを使ったやり取りはどうしても時間がかかりますが、焦らず余裕を持って対応することが信頼関係につながります。

難聴の高齢者のリハビリで気をつけること
一方で、高齢者の難聴に対しては少し異なる工夫が必要になります。
後ろから急に声をかけるのではなく、軽く肩に触れて注意を向けてから話しかけるとスムーズです。
声は無理に大きくする必要はなく、はっきりと区切って発音する方が聞き取りやすいことが多いです。
マスク越しでは口の動きが見えないため、場合によっては透明マスクやフェイスシールドを活用することもあります。
さらに、周囲に雑音があると聞き取りが難しくなるため、できるだけ静かな環境を整えることも欠かせません。
補聴器を使用している方であれば、電池切れや装着のずれによって「聞こえていない」状態になっていないかを最初に確認しておくと安心です。
聴覚に障害がある方に対する共通した配慮とは
いずれの場合も共通して大切なのは、安心して意思を表現できる環境をつくることです。
聴覚に障害がある方は「伝わらないのではないか」という不安を抱えやすく、また高齢の方は「何度も聞き返すのが恥ずかしい」と感じてしまうこともあります。
だからこそ、一方的に話すのではなく、相手が理解できたかを動作や表情で確認しながら進めていくことが大切です。
わかったふりで流れてしまわないよう、相手の反応を丁寧に見ていく姿勢が求められます。

最後に
聾者や難聴の方へのリハビリはきれいごとかもしれませんが、特別な技術よりもまず「伝えようとする心」が大切です。
その思いが伝われば、安心できる雰囲気が生まれ、リハビリの時間が前向きなものに変わっていきます。
お互いにとって温かい関わりになるよう、これからも工夫を重ねていきたいと思います。
〈スポンサーリンク〉