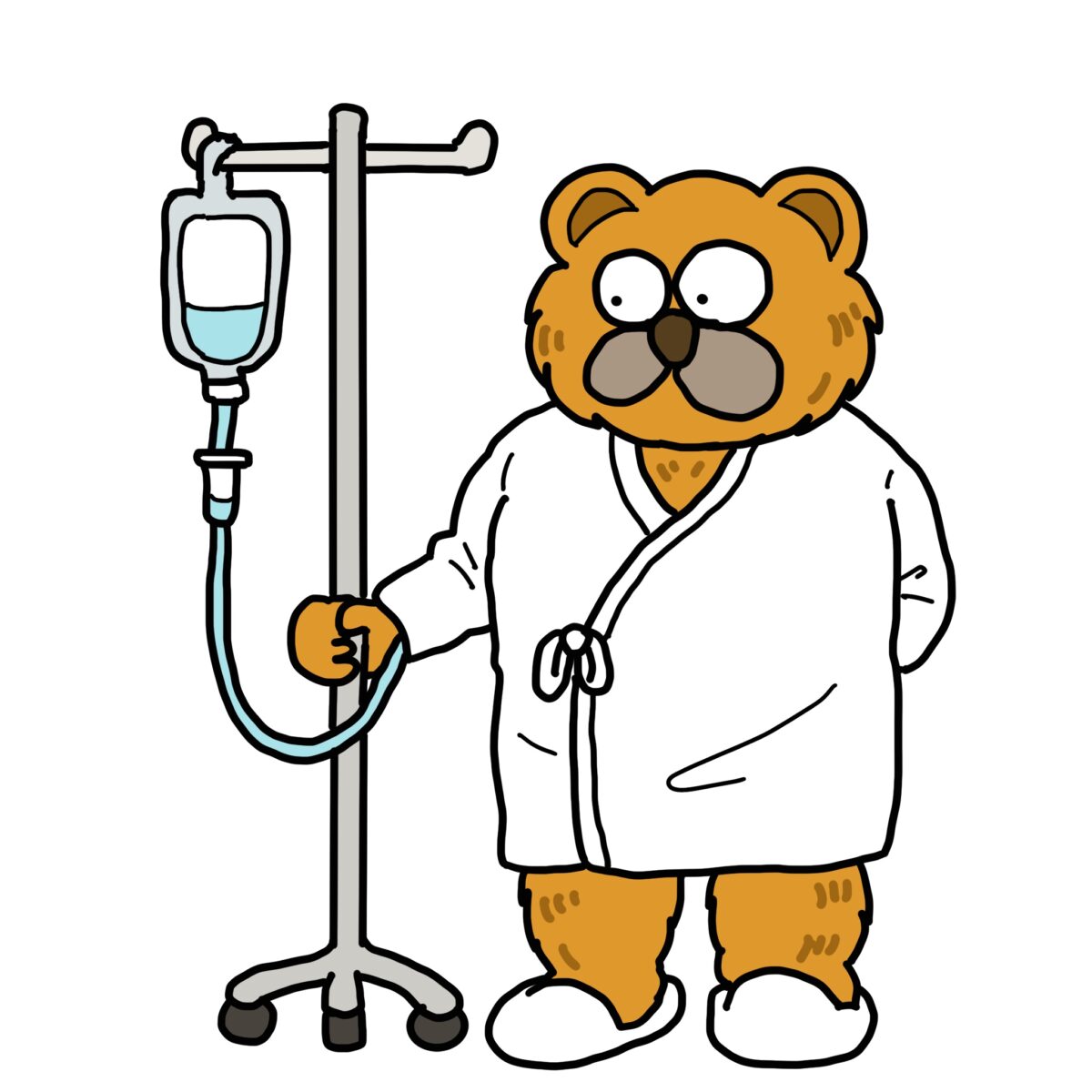〈スポンサーリンク〉
輸液管理、どこまで触っていいの? 〜急性期病院で新人が抱える素朴な疑問〜
新人理学療法士の皆さん、学校で学んだことと実際の臨床現場のギャップに、日々戸惑うことも多いのではないでしょうか。
特に、患者さんの傍らに常に置かれている点滴や輸液ポンプといった医療機器は、僕たち理学療法士にとって「どこまで触れていいの?」と、素朴な疑問や不安を抱きやすいものですよね。
今回は、そんな新人理学療法士さんが抱きがちな、輸液管理における「触れていいライン」について、具体例を交えながら解説していきます。
◼️「輸液ポンプ」は理学療法士が操作してはいけない!
まず、最も明確なルールからお伝えします。
輸液ポンプの流量設定の変更、アラームの停止、ルートの接続・抜去といった直接的な操作は、理学療法士が行うことはできません。
「え、アラームが鳴ってるから止めたいのに…」「ルートが折れてるから直したいのに…」そう思う気持ち、すごくよく分かります。
でも、これらは「医療行為」に該当するため、医師や看護師の業務とされています。

◼️ なぜダメなの?
* 医療行為の独占性:
医師法や保健師助産師看護師法で、医療行為を行える資格者が定められています。
理学療法士は「理学療法」の専門家であり、そのような医療行為を行うことは認められていません。
* 薬剤管理の専門性:
輸液ポンプで投与される薬剤は、患者さんの病態に合わせて医師が細かく指示を出しています。
少しの誤操作が、患者さんの生命に関わる重大な事故につながる可能性があるんです。
* リスク管理:
ポンプの誤操作による過剰投与や薬剤の急速投与、あるいはルート内の血栓形成など、さまざまなリスクを回避するためです。
◼️ 自然落下の点滴、終了後の「逆血」はどうする?
ポンプを使用せず、自然落下で点滴している患者さんの場合、点滴が終わり近くになるとルート内に血液が逆流してくる「逆血」が見られることがありますよね。
「早くクレンメ(流量を調節する器具)を閉めてあげたい!」と思うかもしれません。
でも、ここでも原則は変わりません。
点滴が終了し、逆血が見られた際に、一時的にクレンメを閉める作業も、理学療法士が行うべきではありません。
「病棟に戻るまでに逆血が進んじゃうかも…」と心配になる気持ちは痛いほど分かります。
僕も新人時代、そう思いました。ですが、そこにはいくつかの理由があります。

◼️ なぜダメなの?
* 「点滴終了後の処理」は一連の医療行為:
点滴が終了したと判断し、クレンメを閉める行為は、その後のルート抜去や止血といった一連の「医療行為」の始まりとみなされます。これらは看護師が行うべき業務です。
* 逆血の原因特定と対応の専門性:
逆血の程度や患者さんの血管の状態によっては、血管外漏出やルート内の血栓形成など、看護師による専門的な判断と処置が必要になる場合があります。
* 感染管理:
血液が逆流したルートの取り扱いには、感染管理の知識が不可欠です。
◼️ じゃあ、新人理学療法士は何をすればいいの?
医療現場では、それぞれの職種が自分の専門性を活かし、連携することで患者さんの安全を守っています。
僕たち理学療法士ができる、そしてすべき最善の行動は以下の通りです。
* 直ちに看護師に報告する!
* 輸液ポンプのアラームが鳴った!
* 点滴の逆血が見られた!
* 点滴が終了した!
どんな時でも、「〇〇さんの点滴、アラーム鳴ってます!」「〇〇さんの点滴、終わって逆血してます!」と、状況を具体的に、そして一刻も早く担当看護師に伝えてください。これが最も安全で確実な対応です。
* 患者さんの安全を確保する!
* 点滴のルートが引っ張られたり、患者さんが動いて抜けてしまったりしないように、声かけや体位の調整で安全を確保しましょう。
* 異常を発見した際に、患者さんの顔色や呼吸、訴えなど、他に気になる点がないかも観察し、看護師に伝える情報として準備しておくと良いでしょう。
* 絶対に自己判断で触らない!
* 善意からであっても、専門外の医療行為に介入することは、患者さんを危険にさらす可能性があります。「触らない」という判断が、患者さんの安全を守るためのプロとしての行動です。
◼️ 大切なこと:医療安全はチームで守る
「患者さんのために、何かしてあげたい」という気持ちは、理学療法士として非常に大切な心です。
しかし、医療安全は、個人の善意や判断だけでなく、法的な根拠と職種間の明確な役割分担によって成り立っています。
訓練室から病棟への移動中に逆血が進んでしまっても、それは「理学療法士の業務範囲外である医療行為に踏み込むことによるリスクを避け、看護師の専門的な介入を待つという、医療安全上の判断の結果としてやむを得ない」と理解してください。
この考え方をしっかりと身につけることで、皆さんは自信を持って患者さんと向き合い、安全で質の高い理学療法を提供できるようになります。
不安なことや疑問なことがあれば、必ず先輩理学療法士や看護師に相談してくださいね。
ありがとうございました。
〈スポンサーリンク〉