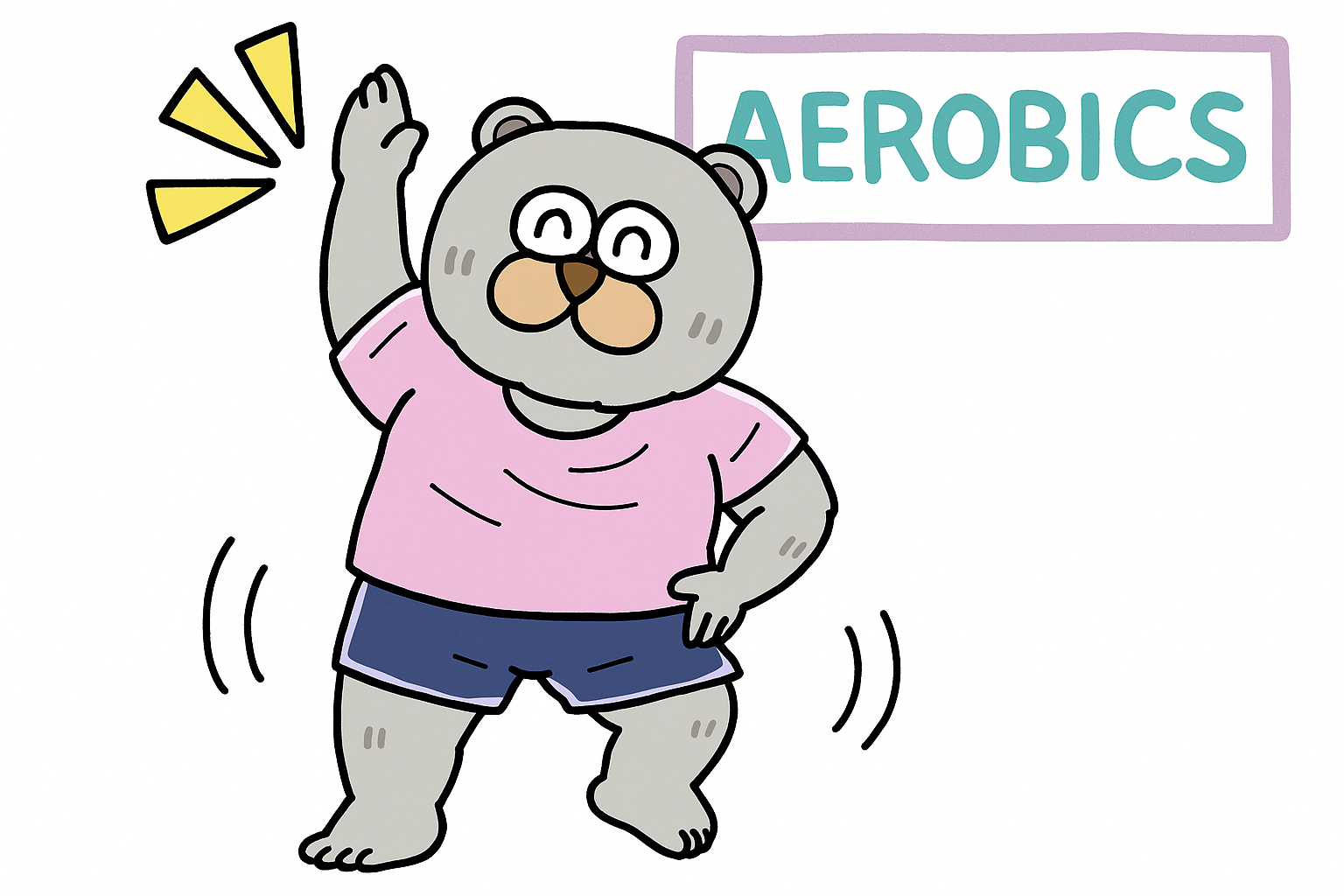〈スポンサーリンク〉
高次脳機能障害と運動の力 〜エアロビクスが効く!〜
今回は、僕自身の経験をもとに「高次脳機能障害」と「運動」の関係についてお話ししたいと思います。
少し前、僕は脳の病気を患い、そこから高次脳機能障害と向き合う生活が始まりました。
記憶力や注意力、段取りを組む力が落ちてしまい、日常のささいなことですら難しく感じることがありました。
入院中には、リハビリの一環としてさまざまな訓練(主に机上での課題)を受けました。
計算問題を解いたり、4桁5桁の数字を覚えて逆唱したり、または図形を並べたりといったもので、確かに少しずつは効果がありました。
でも正直なところ、「これが日常生活にどう活かせるんだろう?」と感じることもありました。
そんなある日、退院後に通い始めたジムで、ふと「エアロビクス」のクラスに出てみたんです。
正直、最初は「リズムについていけるわけがない」「覚えられないだろう」と思っていました。
でも…意外にも、動きの順番が頭に入ってきたんです!
不思議でした。机の前ではなかなか覚えられなかったことが、音楽に合わせて身体を動かすと、自然と覚えられる。
間違えても笑えるし、また次に挑戦しようと思える。
この体験が、僕にとって大きな発見になりました。

なぜ運動が高次脳機能の回復に役立つのか?
実はこのような現象には、ちゃんとした科学的な裏付けがありました。
• 運動をすると脳が活性化する
運動をすると「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質が分泌され、記憶や学習に関わる脳の神経細胞が活発になります。
BDNFを詳しく説明すると、脳内にある神経細胞の成長・再生・維持を助けるタンパク質で、特に「記憶」や「学習」に関わる領域(海馬など)で多く働いています。
具体的には神経細胞の成長や新生を助けたり、またシナプス(神経同士のつながり)を強化して、記憶の定着を促したりします。
つまりBDNFは、脳の柔軟性(神経可塑性)を高める栄養剤のような存在なのです。
• 運動と認知を同時に使うことで脳は鍛えられる
エアロビクスや太極拳のように「体を動かしながら考える」活動は、近年リハビリの世界でも注目されています。
2つのことを同時に行うことを「デュアルタスク」と呼び、記憶・注意・判断力といった高次脳機能を総合的に刺激します。
これは入院中から僕にとっては苦手なことで、セラピストからよく注意されたことです。
• 楽しいことが脳を元気にする
「楽しい」「面白い」と感じるとき、脳内では「報酬系」と呼ばれるネットワークが活性化します。このとき分泌されるのがご存じドーパミンという神経伝達物質です。
ドーパミンは やる気や集中力を高めたり、 記憶の定着を促進する働きがあります。脳にプラスの刺激を与え、回復や学習を後押ししてくれるのです。

僕だけじゃない。誰にでも効果がある可能性
この体験は、僕だけに特別なものではないと思います。
高次脳機能障害を持つ方はもちろん、認知症の予防や軽度認知障害を抱える高齢の方、また脳卒中の後遺症で認知面に課題のある方など、さまざまな方に「身体を動かすこと」は有効だと考えられています。
実際、最近では「コグニサイズ」という、運動と頭の体操(計算やしりとり等)を組み合わせたエクササイズが全国で取り入れられ、効果が報告されています。
これは主に高齢の認知症予防を目的にしたものでますが、高次脳機能障害の方にも十分効果があるのではないかと思います。

おわりに
「机の上のリハビリだけがすべてじゃない」というのが、今の僕の正直な気持ちです。
体を動かしながら、自然と脳も鍛えていく。
そんなリハビリの形が、もっと広がればいいなと思っています。
もし今、同じように高次脳機能のことで悩んでいる方がいたら、ぜひ一度「楽しみながら動く」ことを試してみてほしいです。
少しずつ、でも確かに変化は起こります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
〈スポンサーリンク〉