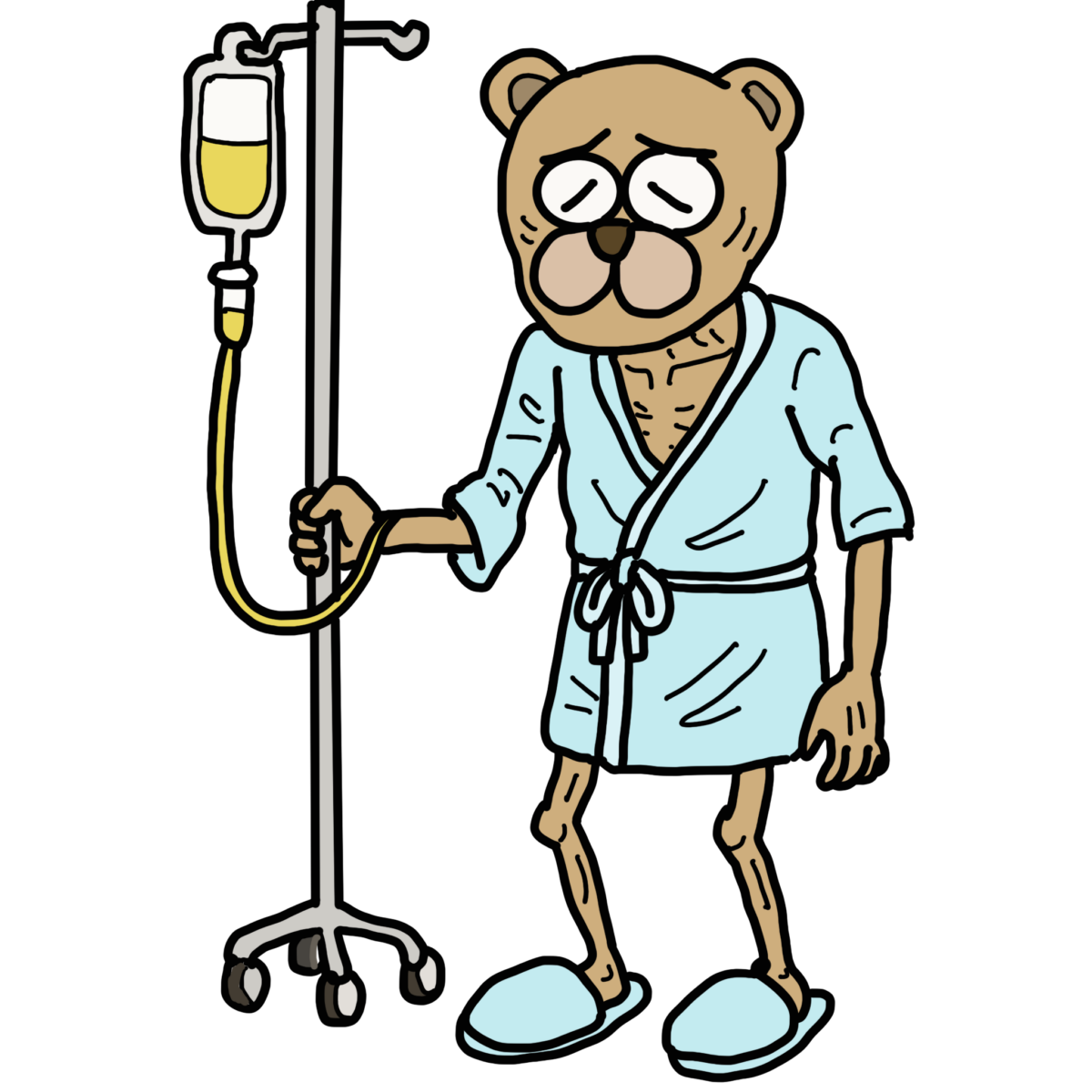〈スポンサーリンク〉
「カヘキシーの状態でも運動はしていいの?」
リハビリや運動療法を行う現場では、こうした疑問をよく耳にします。
特にがん、慢性心不全、COPDなどの進行性疾患において、**悪液質(カヘキシー)**という状態は、患者さんの体力・筋力・栄養状態を大きく損なう重篤な症候群です。
今回は、悪液質の患者さんに対して運動を行うことのリスクと可能性について、理学療法士の視点から解説していきます。
悪液質(カヘキシー)とは?
悪液質とは、慢性的な炎症、代謝異常、栄養不良によって筋肉や体重が著しく減少する状態を指します。
特にがん末期、重度の心不全、COPD、腎不全などで見られ、通常の栄養介入や安静だけでは回復が難しいという特徴があります。
主な症状は以下の通りです:
• 著明な体重減少(特に筋肉量の減少)
• 食欲不振
• 倦怠感、無気力
• 貧血、浮腫
• 代謝の亢進(基礎代謝が高くなる)

カヘキシー状態での運動は「絶対にNG」?
答えはNOです。
ただし「何でもしていい」という意味ではなく、運動の内容・目的・タイミング・栄養状態を正確に評価し、慎重に導入する必要があるという意味です。
カヘキシー患者に運動が推奨される理由
実は近年の研究では、適切な運動が悪液質の進行抑制に寄与する可能性が示唆されています。
■ 有益な効果が期待される点
• 筋萎縮の進行予防
• ADL(日常生活動作)の維持
• 精神的ストレスの軽減
• 廃用症候群の予防
• 消化・循環・代謝の活性化
ただし、これは**「適切な運動処方がなされている場合に限る」**話です。

運動を導入する際の5つのポイント
1. 医師や専門職(PT/OT/ST/管理栄養士)との連携が必須
安全に運動を進めるには、疾患の進行度、炎症マーカー、栄養状態、合併症などを総合的に評価しなければなりません。
主治医の許可があることが大前提です。
2. 運動強度は「非常に軽度〜軽度」
一般的には、**Borgスケールで9〜11(「非常に楽〜やや楽」)**を目安に。
内容としては:
• ゆっくりとした散歩(数分)
• 座位での上肢・下肢の運動
• 寝たきりの方ならROMエクササイズや呼吸訓練
3. 短時間・頻回を基本とする
最初は1回あたり5分以内、1日2〜3回程度からスタート。
疲労感が残らない範囲で、「もっとできそう」で止めるのがポイントです。
4. 栄養管理と運動はセット
栄養不足のまま運動をすると、筋肉はより分解されてしまいます。
運動前後に軽食や栄養補助食品を摂るなど、エネルギー補給とタンパク質摂取が重要です。
5. その日の体調で判断する柔軟性を持つ
悪液質の患者さんは日によって体調が大きく変動します。
無理せず、「今日はやめておこう」という判断もリハビリのうちです。
【まとめ】カヘキシーでも、“正しく”運動すれば意味がある
悪液質は重篤な病態ですが、適切な栄養サポートと医療職のチームアプローチがあれば、患者の生活の質(QOL)を支える運動療法が可能です。
大切なのは、
• 「無理にさせない」
• 「本人の意思を尊重する」
• 「小さな変化を見逃さない」
という視点。
患者さんの「少しでも動けて嬉しい」「散歩が気持ちいい」といった声を大切にしながら、寄り添うような運動療法を目指していきたいですね。
ありがとうございました。
〈スポンサーリンク〉