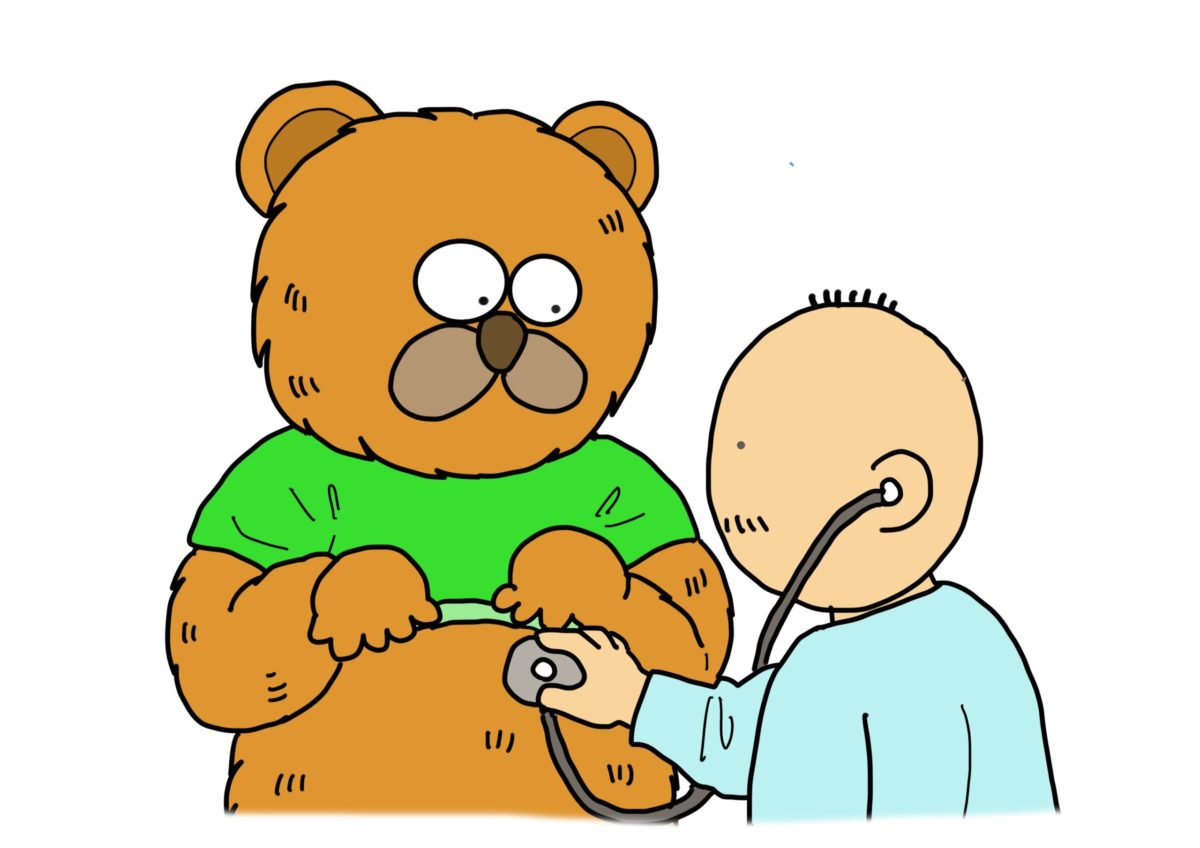- 〈スポンサーリンク〉
ラ音は難しい
ラ音が覚えられないという意見を多く聞きます。
そういう僕もそうです。
日本語でもそれぞれ多くの呼び方があり、ようやく覚えたと思ったら、
病棟Nsからは「コース・クラックルが〜」とか英語で言ってくるので、
日本語と英語がかみ合わなくて訳のわからなくなることも。
どっちかで統一してくれたらいいのにね。
それで結局、カルテには「肺雑+」とか書いちゃってました。
挙句に新人職員から「今は肺雑なんて書いちゃダメなんですよ〜。」と言われる始末。
そこで、今回は副雑音の名前、種類をおさらいして覚えてみたいと思います。
ではいってみましょう。まは連続性ラ音から。
【高音性連続性ラ音(笛声音):ウィーズ:wheezes】

いわゆる「ヒュー音」と言われているものです。
300Hz以上の高音性連続性ラ音です。
気管支喘息などで気道壁が震えることで「ヒューヒュー」という音を発生します。
笛のような音に似ているため、笛声音とも呼ばれることもあります。
例)喘息の他、COPD、気管支拡張症などでも聴取できます。
【低音性連続性ラ音:ロンカイ】

300Hz以下の低音性連続性ラ音と定義。
比較的太い気道で発生するいびきに似た音を発生します。
喀痰などの分泌物の存在を示唆します。
例) COPD、気管支喘息、気管支拡張症、DPBなど
【細かい断続性ラ音(捻髪音):ファイン・クラックル: fine crackles】

5msec以下のことが多く、吸気の後半によく聴かれます。
呼気時に閉塞した末梢気道が吸気時に再開放されるときに発生します。
その解放される音が、肺胞に共鳴します。
「パチパチ」、「バリバリ」と表現されることが多く、
髪を捻るような音に例えられるため「捻髪音」と言われます。
例) IIPs、IPF、石綿肺、過敏性肺炎、肺水腫初期
主に肺疾患の患者で多く聞かれ、気道内の貯留物とは無関係です。
【粗い断続性ラ音(水泡音):コース・クラックル: coarse crackles】

コース・クラックルは粗い感じのクラックル音です。
呼気、吸気いづれも聴取されますが、呼気の方が大きく、吸気の始まりから聴かれます。
個々のクラックルはファイン・クラックルよりも長めで、10msec以上。
太い気道内の分泌液の膜の前後に、吸気時の圧較差が生じ、それが破れるときに発生します。
水泡が破れることから「水泡音」とも呼ばれます。
例) 気管支拡張症、COPD、DPB、進行した肺水腫など。
以上、4つの副雑音について簡単に書いてみました。
やっぱり分かりづらいですね。どうしたら覚えられるんでしょう〜。
少しでも参考になりましたら、ポチっとお願いします↓
〈スポンサーリンク〉